上北山村の伝説
猫と隠し玉
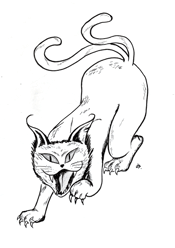
ねこ
山小屋でね、玉を鋳(い)っておったと、猟師が。そして玉を鋳って、こう、鋳型へもっていって流しこんで、そしてポット出して、それを猫が横へついておってね、一つずつこうしてうなずくんやて、いっぱいずつ。
そしてまあ、玉を作って、明くる晩、そしたら大きなお化けが出てきて、そして、えたいが知れんし、その猟師その鉄砲で撃って撃ってした。ところが、その玉を撃ち、作った玉がなくなってしまって、あの、撃ちつくしたというんですわ。そしたら、今度は大きな化け猫が飛びかかってきたいいますね。
ところが、あの、猟師っていうのは、昔の猟師は、まあ、いろいろ信仰関係との結びつきがあって、念仏玉ていいましてね、あの、その玉へ『なみあみだぶつ』と刻みこんだ玉をまた別に一つは誰にも知らせずにたもとへ入れておくというのが、一つの。まあ、供養を兼ね、また自分を守ることを兼ねて念仏玉というのを一発持っておったと。ところが、猫はその念仏玉を持っておる数までは勘定してなっかた。ですから、その化け猫が出たとき、最後にもう念仏玉で撃ったと。そしたら、猫が鍋をかぶって、そして襲うてきておった。そしたら、鍋がその念仏玉で撃ち抜かれて、割れて、そして、その猫が死んでおったと。
―1982年に聞き語り調査による資料より―
伯母峰の一本足

一本だたら
一本足というのは、伯母ヶ峰みいて射場兵庫がね、猟しに行ったて。そしたら、「赤」という名犬がおって、その名犬がワンワン鳴くから行ってみたら大きな猪がおって、撃っても撃ってもこけなかったと。で、最後に動けんように足を撃ちよったというのが始まりですね。そしてその猪に赤も射場兵庫も追わえまわされて、最後に気絶しておったと。そこで赤が射場兵庫の耳元でね、ワンワン鳴くから、射場兵庫が気がついて見てみたら、大きな猪が谷みいてこけておったて。その猪の背中に笹が生えておったということから始まって、あれ、猪笹(いざさ)王というふうに名付けたと言われておるんですわ。
そして、持ちもこたげもならんような大きな象ほどある猪であったということで、あくる日、見に行ったら、その猪はどこかへ姿を隠していなかったんだと。その猪は、この奥通り、ちょうど撃った場所は今の辻堂という山がありますわ、そこのこちらの沢で撃ったですからね。そこは小豆(あずき)横手というとこですわ。今行ってもこの小豆のようなこまかい赤石がずーっとあるところですわ。そして、奥通をずーっと逃げて、湯の峰の温泉へ侍の姿をして、そして湯湯治(ゆとうじ)に行ったと。そしてまあ、あそこの旅館へ泊まって、離れを借りきってね、そして、「俺の寝姿だけは見るなよ」と言うて寝たて。
ところが、まあ、ぞうりを並べにいって見たら、菅で作った大きなわらじが、こう動かそうとしても緒を柱の下へおさえてあったというですよ。だからびっくりして、主人がちょっとすけて見てみたら、八畳の間いっぱいになった大猪が背中に笹生やしたまま寝ておったと。そいで、腰を抜かして這いながら母屋へもどってしておったら、まあ、朝、手を叩いて向こうから呼ぶもんやから、そこの奥さんが代わりに接待に出たと。そしたら、何を隠そう、俺は伯母ヶ峰の山の主の猪笹王というもんやと。あれほど寝姿を見るなと言うてあったのに、お前とこの主人が俺を見てしもうたと。俺の足は射場兵庫に撃たれて、こうしてびっこになっておると。で、湯湯治に来たんやけども、かえすがえすも山奥から追い出されたことが残念やから、山をもういっぺん取りもどしたいということで、一番邪魔になるのは赤という犬とそれから射場兵庫が持っている鉄砲が一番邪魔になるので、それをひとつ買いとってきてくれということで、湯の峰から使いが来て、天ヶ瀬へ小金を持って、ほいで、その犬と鉄砲を買いもどしに来たと。ところが、天ヶ瀬の人たちはいろいろ様子が変であるから聞きとらしたところ、その事実が明るみに出てきて、その者に犬と鉄砲を渡したら天ヶ瀬は野になるぞということで、絶対売らないということになった。ところが、何とか一騎打ちをいどんできて、今の辻堂へみいてかまって(居(きょ)を構えて)ですね、辻堂というのは伯母ヶ峰を越すときに皆そこを通らんと行けんもんですから、そこへみいて猪笹王が一本足のお化けに化けて、かまって、そこでまあ居ついたって。そして、旅人をも取って食べたと。そいて、あの、伯母ヶ峰を使用できんようになってしまったと。
そこへみいて丹誠上人ていう人がね、越えてこられて。お坊さんが。で、丹誠上人ていうのは大台を第二高野(女人高野)のようなかっこうにしたいということでね、まあ、割り合いに体が弱かって、それが完成せずして亡くなったんですけどね、その人が越えてこられたときに来て、「えらい村がさびれておるやないか。」と。だから、どうしたことかというていろいろ村の人に尋ねて、で、こうゆうことでさびれておるんだよということを聞いたもんやから、「その亡霊を私が祈祷して伏せてやろう」ということで、その丹誠上人が現在の伯母ヶ峰隧道の入口にあるお地蔵さん、もとは辻堂にあったんですよ、あの日ぎり(日限をきって願をかける)の地蔵というのをどこからかお迎えしてきて、そして、そこで祈祷をしてですねえ、日をきる、その日をきったのが十二月の二十日です。いわゆる果ての二十日といいますね。それで、果ての二十日、一日だけは鬼が出て人を食べてもよろしいと、その他の日には絶対出てはいけないとして、お地蔵さんに祈願をして、そういうふうにしておさえたわけですね。伏せると言うんですよ。ですから伯母ヶ峰の厄日というのは十二月二十日、果ての二十日になっとるわけですよね。けれどもそれは、旧暦の果ての日です。そういうふうなことで、それからまあ、村の人たちがそこのお堂へみいてつめたり、ま、通行も盛んになって、また、元の景気がもどってきたんだと、こういうんです。これが伝説の本筋なんですよ。
―1982年に聞き語り調査による資料より―
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地
電話番号:07468-2-0002
ファックス:07468-3-0265
お問い合わせフォーム








更新日:2024年02月01日